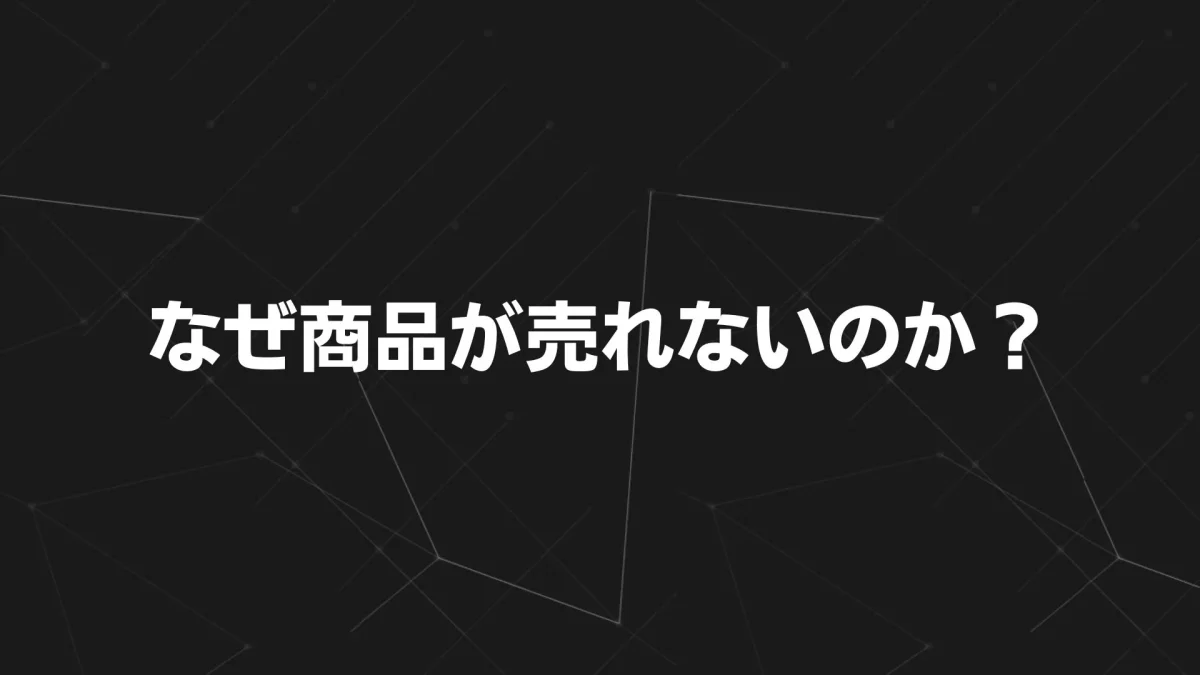「いい商品なのに売れない」
「広告も打ったのに反応がない」
こうした悩みは、多くの中小企業や個人事業主が直面する課題です。だが問題は“商品”ではなく、“マーケティングの仕組み”にあります。
マーケティングとは「売れる仕組みを作ること」。本記事では、森岡毅氏の戦略的アプローチにも通じる「構造的マーケティングの視点」から、売れない原因と解決策を明らかにします。
「商品が売れない」のはマーケティング構造が欠けているから
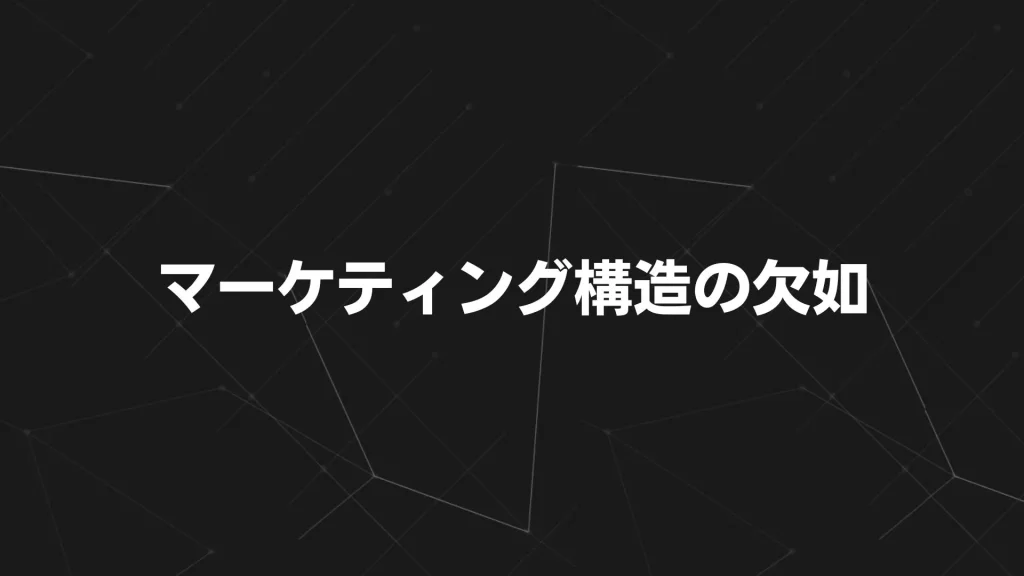
売れない原因は、表面的な広告や販促ではなく、戦略の根本にあります。以下の3つの要素が噛み合っていなければ、どれだけ露出しても売れません。
売上の構造=認知 × 配荷 × プレファレンス
| 要素 | 解説 |
|---|---|
| 認知 | 顧客に商品・サービスの存在が知られているか |
| 配荷 | 顧客が購入できる導線・チャネルが整っているか |
| プレファレンス | 顧客が「欲しい」「信頼できる」と思える選ばれる理由があるか |
このどれか1つが欠けても売上は生まれません。多くの場合、「売れない」原因はプレファレンス不足=“買う理由”の欠如です。
関連記事:【図解あり】マーケティングとは?意味・目的・歴史をやさしく解説
消費者理解が浅いとマーケティングは機能しない

売る側の都合や論理で動いていないか?
誰に、どんな状況で、なぜ買ってもらえるのか?この“消費者理解”が足りていなければ、どんな施策も空振りになります。
消費者理解のための3視点(3C分析)
- Customer(顧客):誰がどんな場面で困っているのか
- Competitor(競合):競合と比較してどこが優れているのか
- Company(自社):自社が提供できる本質的な価値は何か
例:
30代共働き夫婦に向けた時短食品を売るとき、「早くてうまい」ではなく、「子どもとの時間を作れる」「罪悪感が減る」といった“心理的な価値”こそが刺さります。
関連記事:3C分析のやり方を分かりやすく解説|初心者でも実践できるマーケティング手法と事例まとめ
プレファレンスを高めるには、ブランドと体験が必要
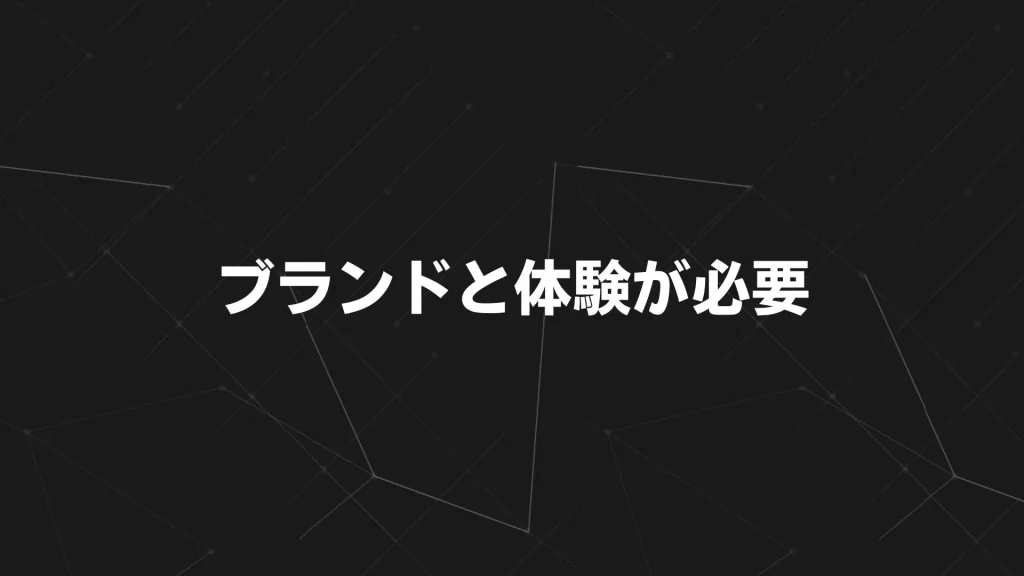
ただの機能や価格ではなく、“意味づけ”がないと人は動きません。ここに必要なのがブランド構築です。
ブランドとは「買う理由の集積」
ブランドはロゴやデザインではなく、「その商品を選ぶべき理由を頭の中に作る作業」。広告だけでなく、接客、レビュー、価格設計、ビジュアルすべてがその材料です。
例:
Appleのように「高価格」でも買う人がいるのは、商品に“信念”や“物語”が込められているから。
売れない商品を蘇らせるマーケティング施策一覧
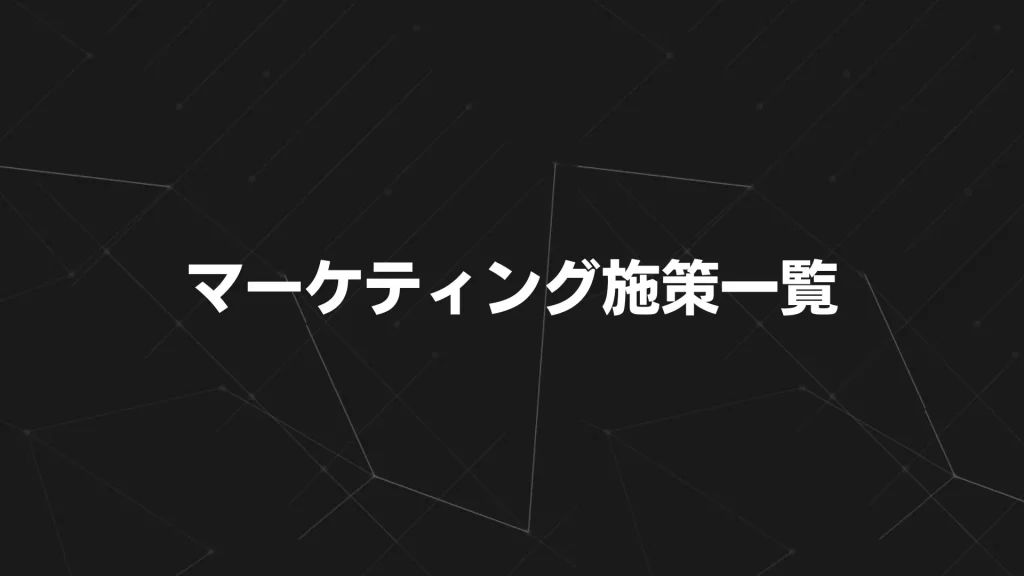
| 項目 | 改善ポイント例 |
|---|---|
| 商品設計 | 顧客視点のベネフィット再設計(例:性能 → 時間短縮・安心感など) |
| 販路・チャネル | オンラインとオフラインの統合(例:Web予約→店舗受け取りなど) |
| 価格戦略 | 単価の見直し/サブスク化/セット販売化 |
| プロモーション | 広告よりも「検索に出る」「知人に語られる」仕組み(SEO・UGC・紹介制度など) |
| ターゲット設定 | ペルソナ精査とCEP(購買のきっかけ)設計 |
加えて、上記の施策を「単体」で行うのではなく、“仕組みとして連動させる”ことが重要です。例えば、ペルソナ設計で明確になったターゲット層に向けて、共感性のあるベネフィットを軸にした商品設計を行い、その価値が自然と伝わるようにチャネル(SNS、SEO、店舗など)を選定。そこに価格戦略やUGCを組み合わせて「試したくなる・語りたくなる」流れを作る。部分最適ではなく、顧客行動の全体設計=売れる仕組みの最適化が求められます。
失敗例から学ぶ“やってはいけない売り方”

- 全部の人に売ろうとする
「ターゲットを絞ると売上が減るのでは?」という不安から、誰にでも通用するメッセージを発信してしまうケース。結果、言葉がぼやけて刺さらず、誰の心にも響かない。「30代共働きママ向け」など、絞るからこそ共感と信頼が得られ、購入につながります。 - 価格でしか勝負しない
価格を下げることは一時的な成果にはつながるものの、競合と同じ土俵での“消耗戦”に突入します。しかも価格に敏感な層はロイヤリティが低く、継続率も悪い。むしろ「なぜこの価格なのか」という価値の物語化こそが差別化につながります。 - 露出だけを追いすぎる
フォロワー数やインプレッションに目を奪われ、肝心の「売れる導線」を見失っているパターン。バズっても売れないのはよくある話で、数字に現れない「共感」や「解像度の高い体験」の設計こそが成果を生む要素です。 - 主語が「自社」になっている
「私たちはこんなに頑張っている」「この商品は優れている」――このような一方通行のアピールは、顧客にとってはどうでもいい情報です。「あなたの悩みをこう解決できます」と、“相手目線”に切り替えることで、伝わり方は劇的に変わります。
まずやるべきは「市場とのズレ」を見直すこと
マーケティングの失敗の多くは、「商品力の不足」ではなく「市場との不一致」です。どんなに優れた商品であっても、求めていない人に届けていては売れるはずがありません。
特に注意すべきは、「時代」と「生活者の文脈」のズレです。数年前は通用していた訴求やチャネルも、価値観やライフスタイルの変化とともに陳腐化していることがあります。
また、売り手が想定しているペルソナと、実際に検索や購買行動をしている層がズレているケースも少なくありません。Google検索やSNSのコメント欄、競合レビューなどを活用し、リアルな顧客の声を拾うことが、ずれを補正する第一歩となります。
「商品に市場を合わせる」のではなく、「市場に商品を合わせ直す」ことが肝要です。
まとめ|売れないは構造の問題。売れる仕組みを設計せよ
「商品が売れない」ことに悩んだとき、まず見るべきは商品ではなく“構造”です。以下を再構築することで、売れる仕組みはつくれます。
- 誰に売るか(ターゲティング)
- なぜ選ばれるか(プレファレンス)
- どこで買えるか(配荷・チャネル)
- どう知ってもらうか(認知設計)
- どう感じてもらうか(ブランド体験)
関連記事
「集客できない理由5選と解決策」もあわせてご覧ください。構造的に“人が集まらない理由”を分解しています → 集客できない理由はこちら