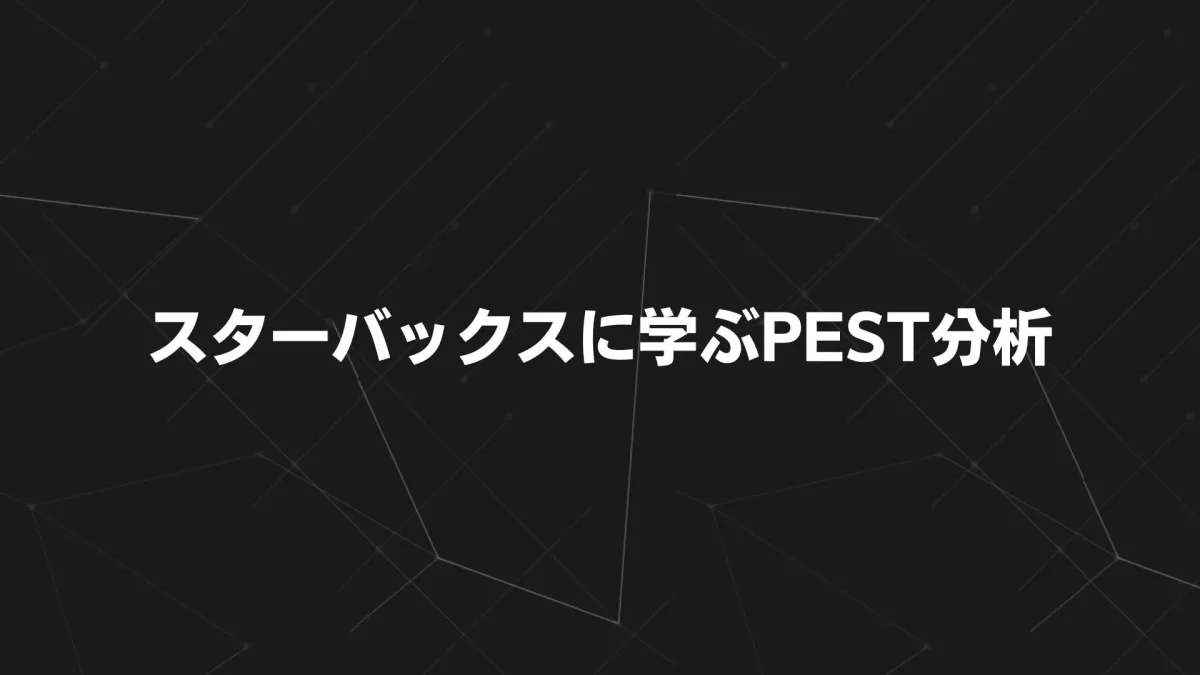スターバックスは、世界中で愛されるカフェブランドとして、マーケティングの教科書にも登場する企業です。しかし、その成長や変化の背景には、政治・経済・社会・技術といった「マクロ環境」の影響が密接に関わっています。
本記事では、スターバックスのビジネスを「PEST分析」のフレームで分解し、それぞれの要因が事業にどのような影響を与え、どのように戦略的に対応しているかを詳しく解説します。マーケティング担当者や経営者にとって、環境要因を見極める視点は不可欠です。実務で活かせる分析と戦略立案のヒントをお届けします。
スターバックスの概要と分析の前提

スターバックスは1971年、アメリカ・シアトルで創業。2024年時点で世界84か国に約38,000店舗、日本国内では1,900店舗以上を展開しています。
日本法人スターバックス コーヒー ジャパン株式会社は1996年に設立され、都心部を中心に拡大。サードプレイス(家庭でも職場でもない第三の空間)というブランドポジショニングを確立し、長期的な顧客ロイヤルティを築いてきました。
今回のPEST分析では、日本市場におけるスターバックスを対象とし、最新の社会動向や技術革新を踏まえて解説します。
Politics(政治・法律的要因)
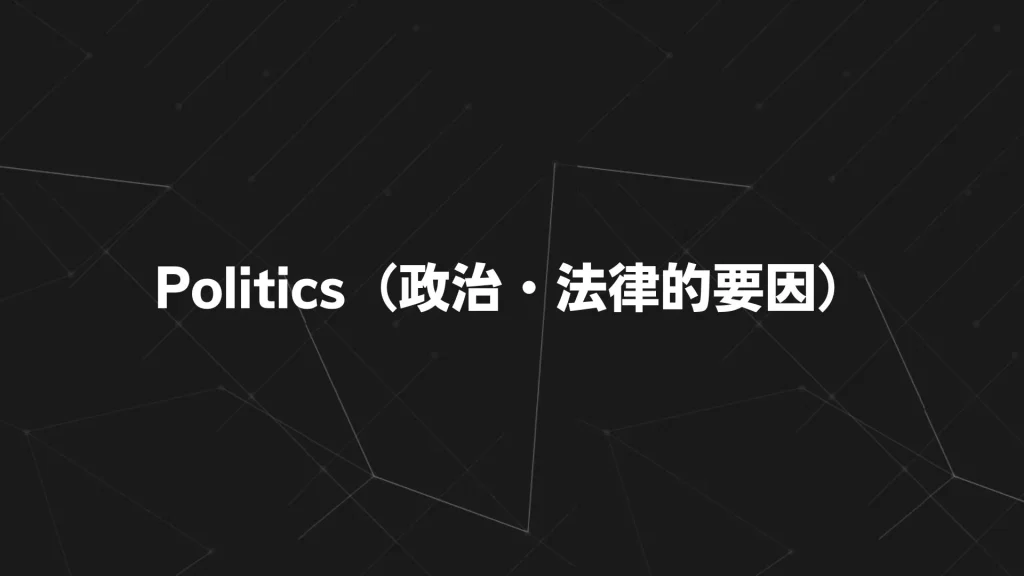
日本でカフェ事業を展開するうえで、政治・法律の影響は無視できません。特に以下のような項目が重要です。
- 消費税の引き上げと軽減税率制度
飲食店のテイクアウトは8%、店内利用は10%と異なる税率が適用され、スターバックスではレジ対応や価格設定の工夫が求められました。
消費者への説明やメニュー表示の明確化を徹底することで、混乱を最小限に抑えています。 - プラスチック削減に関する法規制
2022年に施行された「プラスチック資源循環促進法」に対応し、プラストローの廃止、紙製ストローやリユーザブルカップの導入を進めています。
環境配慮の姿勢をアピールし、Z世代やミレニアル世代の価値観にマッチしたブランディングを強化。 - 最低賃金の上昇と雇用政策
2023年には全国平均で時給1,000円を突破し、店舗運営コストへの影響が大きくなっています。これに対し、スターバックスは「リザーブ店」や「高単価メニュー」の導入により、利益率の確保を図っています。
Economy(経済的要因)

次に、日本経済の動向がスターバックスに与える影響について見ていきます。
- 円安と原材料価格の高騰
コーヒー豆の多くを輸入に頼るスターバックスにとって、円安と輸送費の高騰はコスト構造に大きく影響します。
これに対応し、近年では「ジャパン オリジン」シリーズなど、国産原材料を活用した商品を強化し、地産地消を打ち出す姿勢も見られます。 - インフレによる購買行動の変化
価格に敏感な消費者が増えるなか、スターバックスは「リワードプログラム(アプリによるポイント還元)」の強化でリピーターを囲い込みつつ、「おかわり割引」などの価格戦略でボリューム需要に対応しています。 - 労働人口の減少と人材不足
日本全体で人手不足が深刻化する中、スターバックスは「女性活躍支援」や「シニア採用」、外国人スタッフの登用にも積極的です。多様性と働きがいを両立させる組織文化は、競争優位性につながっています。
Society(社会的要因)

スターバックスが特に敏感に対応しているのが、社会的な価値観やライフスタイルの変化です。
- 健康志向とカスタマイズ需要
近年、低糖質・植物由来・オーガニックへの関心が高まり、ソイ・アーモンド・オーツミルクなどの選択肢を常設化。顧客が自分好みにドリンクをカスタマイズできる設計が支持されています。 - サステナビリティ・エシカル消費
フェアトレード認証豆の使用や「Bring Your Own Cup」キャンペーン、収益の一部を地域支援活動に充てるなど、社会的責任を重視した活動が評価されています。 - 働き方の変化とテレワーク需要
Wi-Fiと電源完備の空間を提供することで、リモートワーカーや学生にとっての「作業空間」としても定着。スターバックス リザーブ®や和モダン店舗は、より高価格帯の需要を満たす場所として機能しています。
Technology(技術的要因)

最後に、スターバックスの技術活用について見ていきましょう。
- モバイルオーダー&ペイの普及
アプリでの事前注文・キャッシュレス決済が普及し、ピークタイムの待ち時間削減とオペレーション効率化が実現。アプリのUIも直感的で、利用者層の拡大に寄与しています。 - スターバックスリワードの強化
来店履歴や購入傾向に基づいたパーソナライズされたクーポン配信により、CRM(顧客関係管理)が進化。デジタルとリアルの融合が進み、ブランドエンゲージメントの向上に貢献しています。 - ESG投資とエネルギー効率の改善
再生可能エネルギーの導入、冷暖房・照明の省電力化などを進め、投資家や自治体との関係構築にもつなげています。
PESTから導かれる戦略視点|SWOT・3Cと連携
PEST分析から得られる示唆は、単なる外部環境の把握にとどまりません。他のフレームと組み合わせることで、より実践的な戦略立案が可能です。
- SWOT分析:
・強み:ブランド力、店舗デザイン、顧客体験
・弱み:価格の高さ、低価格帯への対応力
・機会:健康志向・サステナブルトレンド
・脅威:新興カフェチェーン、原価高騰 - 3C分析:
・顧客(Customer):健康志向、エシカル意識の高い20〜40代
・競合(Competitor):ブルーボトルコーヒー、ドトール、コンビニ
・自社(Company):高付加価値型ブランディング、地域共創型戦略
これらを踏まえると、スターバックスは「健康・サステナブル・ローカル」の3軸でブランドを深化させつつ、DX(デジタル変革)によってCRMと業務効率の両立を図る必要があります。
まとめ|PEST分析で見えてくる未来への布石
スターバックスのPEST分析から見えるのは、外部環境にいかに適応しながら自社の強みを活かすか、という戦略的視座です。
特に日本市場では、少子高齢化や価格競争、環境規制といった要素が複雑に絡みます。しかしそれに対し、スターバックスはブランド哲学を守りながらも、柔軟に商品・サービス・デジタル体験を変化させています。
中小企業にとっても、このようにPEST分析を通じて環境変化を読み取り、変化を機会として捉える力は、競争優位性を築くうえで不可欠です。