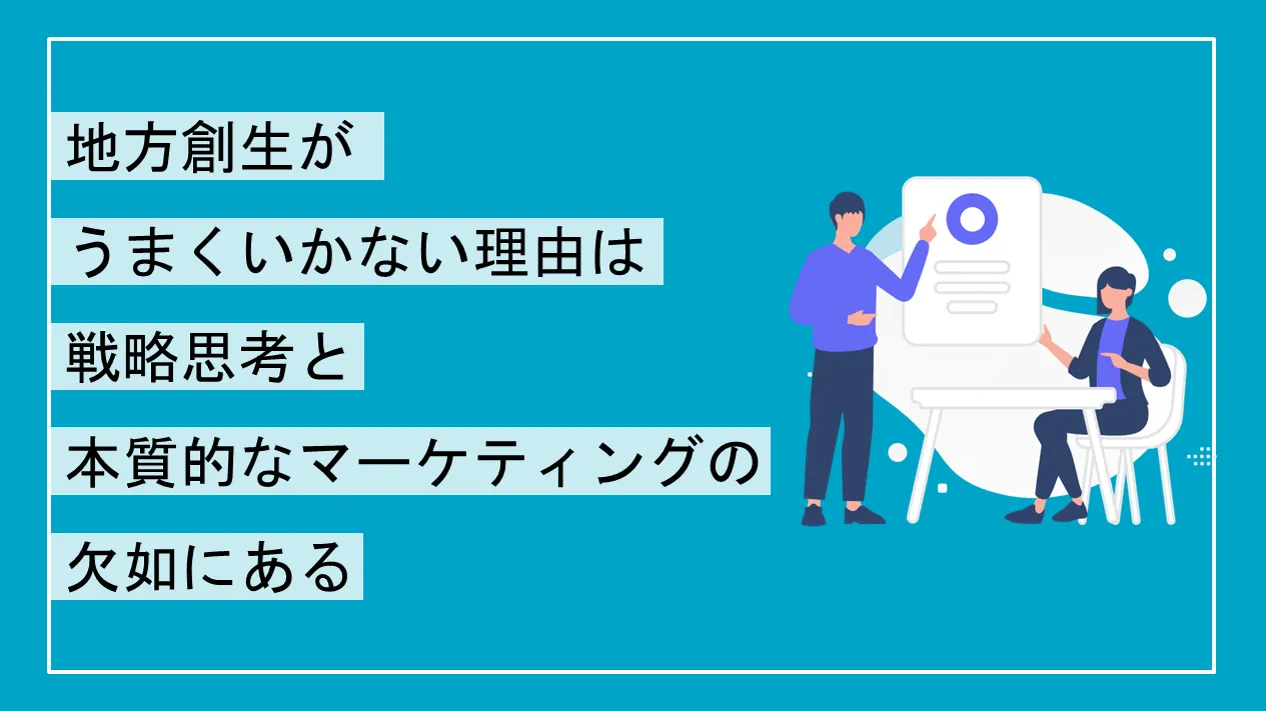地方創生の取り組みが期待通りに進まない理由の一つは、戦略思考と本質的なマーケティングの欠如にあると考えています。多くの地方自治体は、生活者のニーズを深く理解せず、表面的なスローガンや一過性のキャンペーンに依存しがちではないでしょうか?
地方創生に成功するためには、明確な目的設定、戦略仮説の立案、環境分析、そして具体的な施策の実行が不可欠です。地域の魅力を最大限に活かし、持続可能な発展を目指すためには、本質的なマーケティングアプローチと戦略的思考が求められます。これは単なる地域資源のPRや一時的なプロモーションではなく、地域全体のビジョンと計画に基づいた取り組みが必要です。
そこで今回の記事では、地方創生がうまくいかない理由とその解決策として「戦略思考」と「本質的なマーケティング」に焦点を当て解説していきたいと思います。是非最後までご覧ください。
地方創生がうまくいかない理由
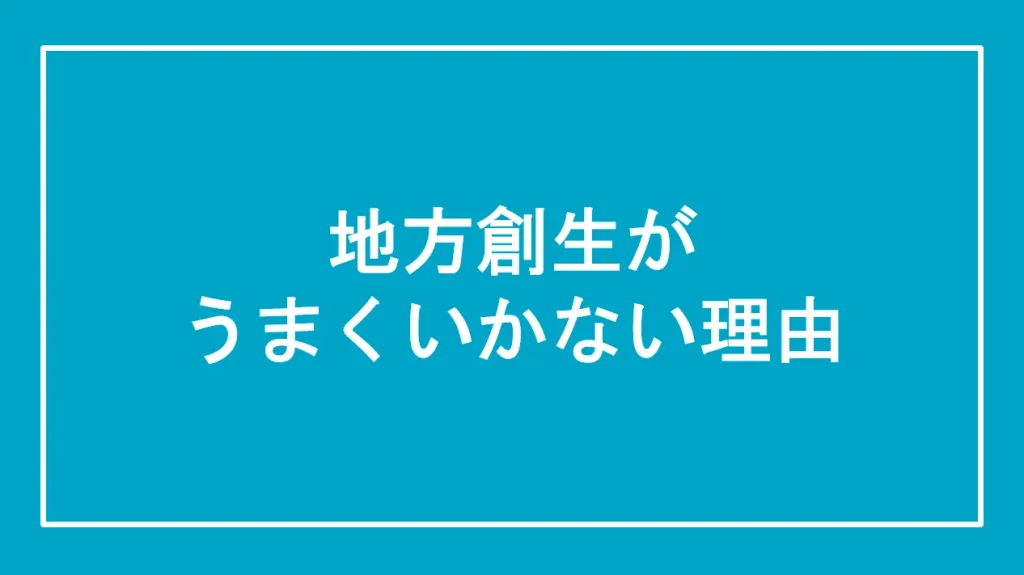
地方創生がうまくいかない理由にはいくつかの課題が存在します。以下に主要な課題を挙げ、それぞれについて解説します。
現地の実情に合わない施策
地域ごとの特性を無視した一律の施策が導入されることが多く、その結果、地元住民のニーズに合わないプロジェクトが実施され、失敗に終わるケースが多いと感じています。例えば他の地域の成功事例をそのまま実施したりするケースがそれにあたります。
地域ごとに置かれている環境や魅力は違う為、成功事例を参考にする事は良い事ですが、そのまま真似する事はお勧めできません。
都市型フレームワークの誤用
上記と似たような理由となりますが、都市部で成功したフレームワークをそのまま地方に適用しようとすると、地域の実情に合わずに期待される成果が得られず、プロジェクトが失敗することがあります 。
都市型フレームワークは都市部の高密度な人口、インフラの整備状況、消費者行動の特性などを前提としています。一方、地方は人口密度が低く、インフラも都市部ほど整っていないことが多いため、同じ戦略を適用しても効果が出にくい可能性があります。以下は都市型フレームワークの例です。
- PEST分析: 外部環境を政治(Political)、経済(Economic)、社会(Social)、技術(Technological)の4つの視点から分析するフレームワーク 。
- SWOT分析: 自社の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を分析することで戦略を立てるフレームワーク 。
- STP分析: 市場をセグメント化(Segmentation)し、ターゲティング(Targeting)を行い、ポジショニング(Positioning)するためのフレームワーク 。
人口減少と一極集中
地方地域の最大の課題は人口減少と東京などの大都市圏への一極集中です。この現象により、地方の労働力が減少し、経済活動が停滞しています 。特に多くの若者は地方を離れ、都市部へ移住する傾向があります。これは教育機会や就職先の多さ、生活の利便性などが都市部に集中しているためです。この結果、地方では高齢化が進み、地域の活力が低下しています 。
若年層にとって東京等の都市部の魅力値は高く、これは地方の努力で解決できる問題ではないと思います。その為、ターゲットを若年層からUターンやIターンを検討している層やファミリー層に絞る事も重要です。
ノウハウの欠如
地方創生を進めるために必要な専門知識やノウハウが不足していることが大きな障壁となっていると感じています。地域の特性やニーズに合わせた戦略を立てることが難しいため、効果的な施策を実行することが困難であることが地方の現状です。
それもそのはずで、そもそも行政で働かれている方々はマーケティングや地方創生のプロではなく、あくまでも地方公務員なのです。地方創生は全くの畑違いであり、通常の業務もある中で地方創生を成功に導く事は並大抵のことでは出来ないと感じています。
圧倒的リソース不足
人材不足:地方では、そもそもの人材が不足しています。これは少子高齢化の進行とともに、若年層が都市部に流出するためです。この結果、地域の重要なプロジェクトを推進するためのリーダーシップや専門知識を持つ人材が不足しがちだと感じます。
資金不足:地方自治体の予算は限られており、必要なプロジェクトに対して十分な資金を確保することが難しい状況です。このため、大規模なインフラ整備や長期的な地域活性化計画を実行するのが困難にな状況にあります。
技術・設備の不足:地方では、最新の技術や設備が整っていないことが多く、これが地域の競争力を低下させる要因の一つとなっている事は確かです。ITソリューションやデジタル化の遅れも、効率的な業務運営を阻害していると思います。
どうすれば地方創生はうまくいくのか?

地方創生を成功させるためには、戦略思考と本質的なマーケティングが不可欠です。以下にその具体的な方法を説明します。
戦略思考を身に付ける事
戦略思考は、限られたリソースを最大限に活用するための方法です。地方自治体においては、人材、資金、時間、物といったリソースが限られているため、効果的な戦略立案が不可欠です。リソースを最適に配分し、最大の効果を得るためには、優先順位を明確にし、重要な施策に集中する必要があります。
戦略思考のフレームワークを簡単に解説すると、目的(Goal)、目標(Target)、戦略(What)、戦術(How)を明確にする事です。以下はあくまで例ですが、戦略思考の参考にしてください。
- 目的:3年で移住者を100人増加させる
- 目標:ファミリー層
- 戦略:教育に力を入れる
- 戦術:日本一のプログラミング授業の提供
上記のようにやる事を決めた場合、このプロジェクトの結果が出るまでは他の施策に着手する事は避けてください。やる事を決めることは、同時にやらない事を決めるということです。特に地方のようにリソース不足が課題としてあげられる自治体では一度決めた戦略をやりきる事が重要です。
※戦略思考についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
本質的なマーケティング
マーケティングの本質は「顧客視点」に立つことです。この言葉を自治体のマーケティングに置き換えるなら「生活者視点」とも言えると思いますが、生活者視点とは彼らのニーズや価値観、さらには内に秘めたインサイトを理解し、それに基づいて価値を提供することを指します。
冒頭にも書きましたが、生活者のニーズを深く理解せず、表面的なスローガンや一過性のキャンペーンを続けていても、生活者にとって価値のあるものでなければ何の意味もありません。正直このような施策はお金をどぶに捨てているようなものですし、一部の悪徳コンサルに搾取されているだけかもしれません。
まずは、生活者のニーズやインサイトを解き明かし、それに沿った形で提供できる「価値」を発見する事が重要です。生活者のニーズやインサイトを理解する為には、アンケート調査の実施や、他の地域の成功事例から読み取る事で理解を深める事が出来ます。また、地域の価値を理解するには地元住民にヒアリングする事も大切です。
このようにして、生活者の求めている事と提供できる価値を理解する事で本質的なマーケティングの第一歩を踏み出すことが出来るはずです。
※顧客視点についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
結論
地方創生を成功させるためには、戦略思考と本質的なマーケティングが不可欠です。人口減少や高齢化、経済の縮小といった課題に直面している地方自治体は、リソースを最適に配分し、生活者の理解を深める事で、地方創生を成功に導けると私は考えています。
もし地方創生についてお悩みの場合、無料で相談も受け付けていますので是非お気軽にお問い合わせください。